お母さまも料理上手で、日本の四季や歳事に合わせた料理やしつらえが、いつも身近にあった野村友里さん。留学や仕事で海外生活を経験し、出会った人たちやシェフと接することで、改めて日本食や文化について考えるようになったそう。野村さんの「今」を作ったその原点について聞いてみた。

海外生活を経て日本の食や
文化を改めて考えるように
野村さんは大学卒業後、「狭い世界から飛び出したくて」イギリスへ留学。目的がなければ説得できないと思い、『料理を学びに行かせて欲しい、料理ならいつでも役に立つから!』と、ご両親に人生で最大のプレゼンをしたのだとか。渡英後はフィニッシングスクールで学びながら、当時全盛期だったコンランショップに大きな刺激を受けたという。

「その頃のコンランは、味の追求だけでなく、食を楽しむ人たちが心地よく過せる総合空間をプロデュースするという考えを打ち出していて、その考えに基づいたレストラン事業も成功していました。家具や照明などの室内装飾から飾るお花までが、食を楽しむことの延長線上にある。その考え方が当時の私にとって興味深く、大いに刺激を受けました。帰国すると、東京でもそうしたコンセプトのレストランが少しずつでき始めていて、その立ち上げに関わったりしているうちに、食の仕事に携わるようになったのです」
その後、しばらくの時を経て、アメリカのバークレーにあるレストラン「シェ・パニーズ」でも働くことに。地元産の有機栽培食材を用い、カリフォルニア料理を新たな方向へ導いたといわれる、アリス・ウォーターズが率いる全米屈指のレストランだ。
「シェ・パニーズで学んだことは、すべてをオープンにするということ。食材の生産者や産地、そしてどういうルートでここまでやってきたのか。それをすべて明快にして人とシェアするという考え方に、居心地の良さと自由さを感じ、今も自分の中でとても大切にしています。仕事をともにしたシェフたちとは、ずっとつながりがあるし、彼らが日本に来て、私の仲間たちと一緒にいろいろなことをして、新たなつながりも生まれているんです」
自分がいいと思ったことは、
多くの人とシェアしてつながりたい
「外国のシェフと話していると、いろいろな気づきもあって楽しいですね。日本の食や文化について質問されることも多くて。例えば『かつお節はどうやって作るのか、なぜ削って使うのか』とか、『この盛りつけ方の意味は?なぜそうするのか理由を教えてくれ』と。思いがけない質問をされ、答えられないこともありました。彼らは和食の技術だけでなく、その背景にある文化まで知ろうとするのです。かつお節まで自分で作りたいと言い、枕崎まで行って作ったこともありました(笑)。日本人の私たちだって、かつお節がどんな工程を経てできているか、知っている人は多くないですよね。そんなことがあると、今までと視点が変わるというか、日本の食文化について、もっときちんと知ろうという気持ちが湧いてくるのです」

かつて「食」をテーマにしたドキュメンタリー映画を製作するほど、野村さんの活動は多岐に渡っている。今後の野望はあるのだろうか?
「野望?ないです(笑)。ただ限られた時間の中で、意味が見出せることに関わっていけたらと思っています。食材がないと料理はできないし、その食材にはいろんな人が関わっている。自分がいいと思う食材を使うのはもちろん、私の店が生産者の皆さんを知ってもらうための媒介になれたらうれしい。いいと思うことは、ひとりでも多くの人たちとシェアしたいし、そういうことで人とのつながりも生まれますよね。人とのつながりは、新しいことを生み出すパワーになると思うのです」
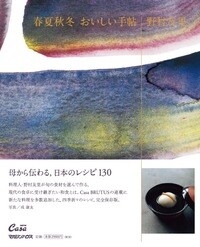
『春夏秋冬 おいしい手帖』
野村友里 著 マガジンハウス刊 2900円(税別)
野村友里が作る、母たちから受け継いだ日本のレシピ130。旬の素材と昔ながらの製法で調理された和食を、写真家・戎康友の視点で鮮やかに切り取る。『Casa BRUTUS』で4年続いた連載に新しい料理を多数加えた、完全保存版のレシピ本。
構成/川端里恵(編集部)


























Comment