皆様に僕と同じように自分の父親と家族の邂逅を文章化して本にしろ、とは絶対に言えない
鈴木:その拒絶は、姉の中には非常にあったと思うんです。姉には姉の許容してきた父の像があるわけで、なんでそのままで終わらせられないのかって。でも、モザイクがかかったままの人物がヘイトを言ったとき、モザイクがかかっているからこそ、よそで同じヘイトを口にしている人の仮面を、モザイクの上に被せてしまうんです。それが僕のやらかしたことであり、いま世の中で分断分断と言われているものの正体って、それかもしれないと思うんです。なので、ある程度モザイクの解像度が高かったり、せめてベースになっているのが何色なのかぐらいわかっていれば、相手が何を言ったとしても、自分が一番嫌っている「分断の主体」の仮面を相手の上に被せることを、しないで済むんじゃないかと。モザイクが剥がれないにしても、ある程度解像度を上げる作業はやった方がいいのかなと思います。
青山:この本を読む限りでは、大介さんのモザイクのかかり方が、クリアに見えるか、あまり見えないか、割と極端な気がしたんです。「デイリー新潮」の記事が出て、家族が大きく傷ついた、大介さん自身も傷ついた。だってお父様が亡くなって2ヵ月ですよね。親を看取るって大変なことで、簡単に整理できない気持ちがあって当たり前に思います。あの記事を書かなければ家族の間だけで、小声で「どうだったんだろう」と話し合えたレベルのことかもしれない。ただ、記事として残ったからこそ検証して本になったと思うし、そういうことを教えてくれる本でもあるとは思うんですが。いやあ、難しい……。
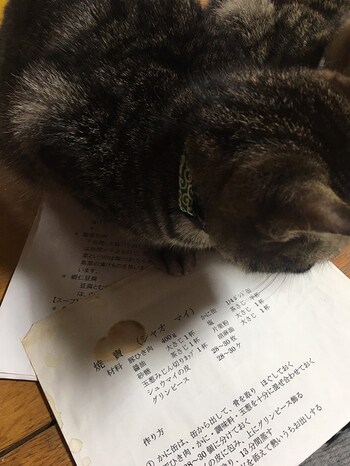
鈴木:難しいですね。あの記事を書いたときは、目の前に真っ赤なフィルターがかかっているぐらい、父を変えた何かに対しての怒りが凄くて。だからと言って、変わる前の父に対しての愛情があったのかというと……そういうことも含めて、思考停止している状態でしたね。書籍の当初の企画にしても、ネット右翼だけでなく、世の中を分断する色々なものについて、色々な敵を明らかにして書きたい、という意図があった。
ただ、書き手は一般の人のような生き方はできない、と僕は思っている部分もある。「掘り下げなければならない」という自分自身の生き物としての性もありますし、自分の失敗や成功を言語化して読者様のお役に立てればっていうのが書き手なので。なので、皆様に僕と同じように自分の父親と家族の邂逅を文章化して本にしろ、とは絶対に言えない。したら多分、家族が壊れるか、死んじゃう人もいるかもしれない。誤った仮面を自分の大事な人に被せていないか、大事な人に対して何か失われたと思っているのは自分が何かを被せてしまっていないか、解像度を上げるための作業方法など、エッセンスだけ抽出して届けば、と思っています。
青山:家族との関わりを考える、大きなきっかけやヒントをもらえる一冊ですよね。私も宿題が山盛りです。カウンセラーの信田さよ子さんが「DVの加害者は変われるか」というテーマで話されるなかで、加害者プログラムでは行為を否定するけれど人格は否定しない、「行為と人格をわける」とおっしゃっていたことも思い出しました。この本は、特に後半の密度がすごい。自分が痛いところも避けずに徹底して取材を重ねて、前半とはテーマも密度も変わっていくように感じました。ご家族の証言はじめ、大介さん以外の視点が丁寧に入ってきて、できるだけバイアスをかけずに人の声に耳を傾けて、その声を受け取ろうとする気配が、読み手の胸の奥に伝わってきます。それがこの本の本当に大きな核というか強い芯になっていると感じました。
鈴木:確かに今回の本、登場人物がめちゃくちゃ優秀でしょう(笑)。叔父はずっと小中学生相手に新しい価値観を仕入れてきた教育者なので、メタでものを見られる、ものすごくフラットな人。姪っ子はすごく直感的な部分と、高い言語化能力があるので、すごい示唆をくれる。さらに父の親友が、父を代弁してくれるような部分がすごくあって。むちゃくちゃ話しやすいのに、でもご自分の娘さんたちとはあんまり上手く話せないという、父と同じような壁を持っている。そういうことも含めて、父にこんな味方がいてくれたことが、何よりも嬉しくて。
































Comment