日曜の夜が待ちきれない! 7月の放送開始から毎週私たちを楽しませ、勇気づけてくれるドラマ『半沢直樹』。その原作者・池井戸潤さんが、まもなく新刊『半沢直樹 アルルカンと道化師』を発表します。謎めいたタイトルのシリーズ最新作では、半沢が探偵に? ひと足早く、その物語をご紹介します。

池井戸潤
1963年岐阜県生まれ。慶應義塾大学卒。’98年『果つる底なき』で江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。2010年『鉄の骨』で吉川英治文学新人賞、2011年『下町ロケット』で直木賞を受賞。主な著書に「半沢直樹」シリーズ、「下町ロケット」シリーズ、「花咲舞」シリーズ、『空飛ぶタイヤ』『ルーズヴェルト・ゲーム』『七つの会議』『陸王』『民王』『アキラとあきら』『ノーサイド・ゲーム』などがある。最新刊は『半沢直樹 アルルカンと道化師』で、9月17日発売。
1枚の絵画に隠された真実とは?
6年ぶりの『半沢直樹シリーズ』、まもなく発売!
「ドラマは毎週見ていますよ。すごいですよね、顔の圧が(笑)。企業買収のストーリーがよくわからなくても、熱い演技を見ているだけであっという間に時間が過ぎていくでしょう? わらったり驚いたりして消費カロリーが高いから、けっこうフィットネスにもなるんじゃないのかな。先日、疲れていて放送中にうっかり寝てしまったんですが、そういうときに限って視聴率が上がったりする。だから、縁起を担ぐなら、僕は放送時間には寝ていたほうがいいのかもしれません」
笑顔で語る池井戸潤さん。スーパー銀行員・半沢直樹の生みの親にとっても、ドラマは「先が読めない、驚きの場面の連続」なのだとか。最終回まで、まったく目が離せません。
そして、クライマックスを前にした9月17日に、シリーズ6年ぶりの新作となる小説『半沢直樹 アルルカンと道化師』が発売されるのも、ファンにとっては気になるところ。現在放送されているドラマの時代よりも時計の針を少し戻して、半沢直樹が大阪に勤務していた融資課長時代を舞台にした物語では、なんと彼が「探偵」となって、ある謎を追うというのですが……。
「もともと僕は、江戸川乱歩賞(推理小説の新人作家登竜門)でデビューしたミステリ作家。『半沢直樹シリーズ』をはじめとして、今まで発表してきた『下町ロケット』も『陸王』も『ノーサイド・ゲーム』も、実はミステリやサスペンスの手法で書いた小説なんです。あるとき、画集に載っていたアルルカンとピエロを描いた絵画を見ていて、新しい半沢直樹の物語に絵画を道具立てにしてみたらどうだろう? と思いついたのが、この物語でした」
人のために《倍返し》。
けっこういいヤツなんです
老舗美術出版社の買収を上役から指示された半沢が、その案件に疑問を抱き内偵を始めると、経営者一族のお家騒動、そしてかつて会社に関わった、若き芸術家たちの秘められた物語が浮かび上がります。ビジネスの現場を入り口にしながら、辿り着くのは深く、濃厚な人間の物語。ある人物が抱えた秘密が明かされる場面では、その悲痛さに、思わず胸が詰まります。
「あの場面を書かなきゃいけないことはわかっていたんですが、どうしても書きたくなくて、先延ばしにして、最後にやっと書きました。でも、この物語で書いたように、中小企業の経営者に銀行員が貸すお金というのは、その経営者の人生に直結したお金なんですよね。そのあたりが巨大企業を相手にした場合とは違っていて、規模が小さいがゆえに、人間とその人生に肉迫できるんじゃないかと。そんな半沢の、血の通った戦いを書きたいと思いました」
半沢直樹といえば、の決め台詞《やられたら倍返しだ》も、大事な場面で登場。しかし、『アルルカンと道化師』を読むと、彼が決して自分の恨みを晴らすために《倍返し》しようとしているのではないことが、よくわかります。半沢、ますます好きになりそう!
「腹黒いんですが、わりといいヤツですよね(笑)。もちろん、銀行の組織内でのチャンバラ劇も今まで通り繰り広げられますから、安心して楽しんでいただけると思います」。
→池井戸潤さんのインタビューは後編(9月19日公開予定)に続きます。

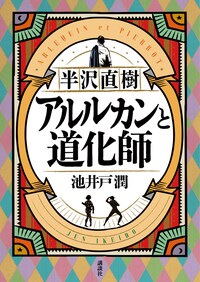
<作品紹介>
『半沢直樹 アルルカンと道化師』 池井戸潤
9月17日発売・講談社 1600円(税別)
東京中央銀行大阪西支店の融資課長・半沢直樹のもとに、業績低迷中の美術系出版社の買収案件が持ち込まれる。
強引な買収工作に抵抗する半沢は、やがて背後に潜む秘密の存在に気づく。探偵・半沢が「絵画」の謎に挑む!























![いま買って初秋まで使える「シャツ&ブラウス」おすすめの素材やデザインは?スタイリスト水野利香が解説![PR]](https://mi-mollet.ismcdn.jp/mwimgs/a/4/80/img_a4ab888660a4986eed6b44c379c032c0257273.jpg)









1