守り抜かれてきた手話は独自の言語
五十嵐:社会問題を扱うならば、やはり製作者は問題について考えるきっかけを作るという意識が必要だと思いますし、受け取る側も「感動した」で終わるのではなくて、例え行動に移せなかったとしても、忘れないで欲しいなと思います。ドラマでいうと90年代に『愛していると言ってくれ』『星の金貨』というろう者が登場するドラマが流行った影響で、手話ブームが起きたんです。「手話ってなんか格好いい」と手話を始める人が増えたんですね。
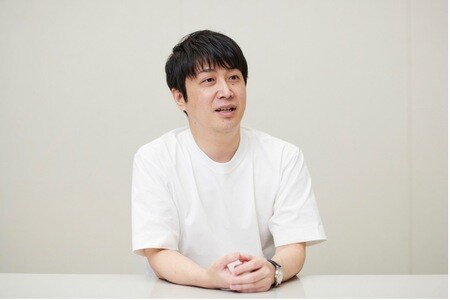
五十嵐:ただ、その時手話を習った人が今どれだけ残っているかなと思ったりすることがあります。
今回も、ドラマ『Silent』の影響で、TikTokなどで振り付け動画のような感覚で手話をしてみた動画が流行ったんです。でも聞こえる人が聞こえる人に向けて発信しているものばかりで、そこには当事者が不在なんです。
手話の動画を見て手話をやってみようという、きっかけとしてはいいと思います。でも、ブームに乗っかって始めて、飽きたら終わり、となりそうだなと。それが悪いとは言い切れないかも知れませんが、リスペクトは必要だと思います。マイノリティの文化って、飽きたらポイ捨てできるおもちゃじゃないので。
──五十嵐さんのご著書『聴こえない母に訊きにいく』を読んで感じたのは、手話というのはろう者の中で独自に生まれた言語である、ということです。当事者にとってはすごく切実で必要なものなんですよね。
五十嵐:手話は独立した言語なんです。福祉のツールのように捉えている人も多いですがそうではありません。過去には手話は差別的な視線を浴びて、禁止されるということもあったんです。ろう学校でも、口話の練習をさせられたという人もいて、実際僕の父も、目の前に紙を垂らされて、紙が動いているかどうかで声が出ているか確認する、という方法で聴者の言語を練習させられていました。そんな中でも、手話は自分たちの言語だからとろう者が守り抜いてきた。そんな歴史を知っていたら、おもちゃにはしないと思うんです。だからあらためて、「知ること」って大事だなと感じます。
──手話を使いたい人が使えるというのは当たり前ではなくて、手話を使うことすら親族から反対されて、聴者と同じようにしゃべるように強制されることもあったというのは、五十嵐さんの本で初めて知りました。
五十嵐:僕たち聴者の日本語話者は、日本で日本語を禁じられることってほぼないと思うんです。ただ、ろう者の歴史においては、自分たちの言語である手話が禁止されるということは普通にあった。自分は聴者というマジョリティとして、いかに恵まれていたかを突きつけられた気がしました。






















Comment