過剰に可哀そうに見せる演出に感じた違和感
五十嵐大さん(以下、五十嵐):ノンフィクションの作品であれば、事実を伝えること、当事者を傷つけないことが大前提だしすごく重要な一方、フィクションの作品の場合、エンターテイメント性は必要です。だから当事者の気持ちのことを考えたときに描き方としてどこまで許して、どこまでが許してはいけないのか、その線引きが非常に難しくなりますよね。
例えば僕が貧困とか親子関係の問題やDVについて描かれているものを見ると、自分に経験がない、当事者性がないので、凄まじい話だなあと圧倒されてしまう。でも、自分に関係してくる、ろう者の人が出てくるものだと、結構厳しい目で見てしまいます。
──フィクションと言えば、昨年放送され、大きな話題となった、中途失聴者が主人公のドラマ『Silent』を五十嵐さんはどう見ましたか?
五十嵐:『Silent』にはいいところと悪いところがあったと感じています。いいところはドラマを通して若い人にも手話やろう者のことが広まったことです。ドラマをきっかけに手話の勉強を始めたという声も耳にしたので、それは素敵なことだなと思いました。
一方でひっかかるところもありました。例えば、夏帆さんが演じるろう者の奈々が、耳が聞こえる自分を想像してスマホに耳をあてるというシーン。もしも私の耳が聞こえて、電話ができたらどうだったんだろうという演出です。あくまでも奈々という女性の過去や性格を踏まえての行動なので否定はしませんが、やはり涙を誘っているんだろうなという印象は強かった。
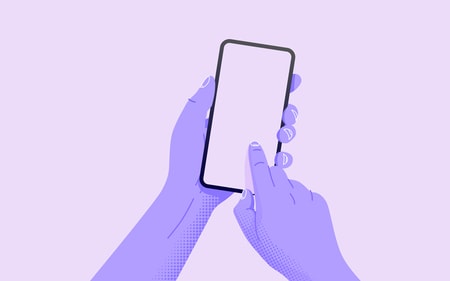
──そう言われてみると、あくまで聴者が、耳が聞こえるのがいいという前提で描いたろう者という感じもします。私は全話は見ましたが、2話くらいでもう見るのがしんどくなってしまったんです。ろう者の困難が描かれるときに、ものすごく切ないBGMが流れて、ここで泣け!という圧がすごくて。障害者は可哀そう、という前提をすごく感じたんです。
だからって全部悪いドラマだったかというとそうではなくて、すごく丁寧に、手話だったり、人間の葛藤が描かれていたと思います。
五十嵐:僕は基本的にどんなやり方であれ、まずは社会問題を知ってもらうことが大事だと思っているんです。だから、ろう者や彼らの側にいる人たちのことを描く作品が出てくるのはすごく嬉しい。
でも、ドラマ『Silent』でどうしても憤りを覚えたのが、中途失聴者である主人公の姉が子供を産んだときのエピソードです。自分の子供ももしかしたら聞こえないかもしれないと不安になるシーンだったんですが、その気持ち自体はわからなくもないんです。そして実際生まれた子供の耳が聞こえて良かった、と安堵する。ただ、その子供に「ゆうき」という名前を付けるんですが、漢字だと「優生」なんです。そう、優生保護法の優生と同じ。それが本当に信じられなくて。音で聞くと「ゆうき」なのでわからないけれど、字幕で見ると「優生」という漢字が当てられていると分かる。そして字幕を見ているのって、基本的にはろう者なんです。
──二重にグロテスクだし、あえてわざわざその漢字を持ってきたことへのフォローがないんですよね。このシーンは当事者を中心に、大きな議論になりました。
五十嵐:今全国で優生保護法※の裁判が行われていて、中にはろう者の方もいらっしゃる。ろう者や手話をドラマで描くならば、ある程度調べるはずです。だからこそ、あのエピソードにはもう少し説明が欲しかった。
※1948年から1996年まで存在した日本の法律。「不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」を目的とし、優生手術(不妊手術)及び人工妊娠中絶が行われた。その対象に聴覚障害者も含まれた。不妊手術を強制された人たちが、全国各地で国に賠償を求め裁判を起こしている。






















Comment