4月3日、文芸誌『群像』(小社刊)主催のトークイベントが講談社で開催されました。登壇したのは、私小説の名手として知られる佐伯一麦さん、日本語とドイツ語の二言語で作家活動を続ける多和田葉子さん、小説、詩、評論と多彩な表現を展開する松浦寿輝さんの3人。そして当日のスペシャルゲストとして、精神の深層に分け入る重層的作品が特徴の古井由吉さんも参加し、「危機の時代、文学の言葉」というテーマで4人が思索を深めていきました。

作家は、自分の内面にある言葉を“翻訳”して書いている
1982年からドイツに拠点を置く多和田葉子さんが一時帰国中で、今回のトークイベントに参加されました。多和田さんは昨年12月にアメリカで最も権威のある文学賞の1つとされる「全米図書賞」を受賞し、「村上春樹と並んでノーベル賞に近い」とも言われ、世界的にも注目度の高い作家として知られています。

多和田葉子(たわだ・ようこ) 1960年、東京都生まれ。小説家、詩人。82年よりドイツに在住し、日本語とドイツ語で作品を手がける。92年『犬婿入り』で芥川賞、2011年『雪の練習生』で野間文芸賞、2018年『献灯使』で全米図書賞を受賞。近著に『地球にちりばめられて』。
「全米図書賞」を受賞したのは、『献灯使』の英語版(マーガレット満谷・訳文)。大災厄を経て、鎖国状態となった日本を描いたディストピア小説の感想からトークは始まりました。

『献灯使』多和田 葉子
大災厄に見舞われ、外来語も自動車もインターネットもなくなり鎖国状態の日本。老人は百歳を過ぎても健康だが子どもは学校に通う体力もない。義郎は身体が弱い曾孫の無名が心配でならない。無名は「献灯使」として日本から旅立つ運命に。大きな反響を呼んだ表題作など、震災後文学全5編を収録。
佐伯 多和田さんと僕はデビューも近く、ずっと同時代の作家として影響や刺激を受けてきました。『献灯使』はディストピア小説と言われることが多かったけど、近未来の中に、日本にかつてあった“鎖国”が取り込まれていて、過去が照射されています。大きな危機が起こった時に、そこから未来への創造力というものが発揮されることが多かったんだけど、その前にまずは過去をもう一度検証することが大事ではないかと感じました。

佐伯一麦(さえき・かずみ) 1959年、宮城県仙台市生まれ。上京して雑誌記者や電気工などさまざまな職に就きながら、91年『ア・ルース・ボーイ』で三島由紀夫賞、2007年『ノルゲ Norge』で野間文芸賞、2014年『還れぬ家』で毎日芸術賞を受賞。近著に『山海記』。
佐伯 多和田さんはずっと言葉の魅力を追求してこられた作家だと思うのですが、言葉や言語というものは分断を招くこともあれば、他者の言葉に対する関心が、異国間の人々を結びつけることにもなります。ここに集まった僕以外の3人の作品は翻訳もされています。僕は翻訳とは縁のない文学生活を送ってきましたが、作家には自分の言葉を翻訳して書くというところがあると思っていて、そういう意味では僕も、自分の中にある言語というものに対して関心を抱かなければ、表現というものはなかなか成り立たなかったのではないかと考えています。
松浦 このトークイベントでは、「危機の時代」というタイトルが掲げられています。多和田さんはドイツ在住で、世界のあちこちを移動しながら、さまざまな意味で危機的状況にある世界を、現在、近未来だけじゃなくて過去にまでさかのぼって小説の言葉にしていらっしゃるので、このタイトルに一番ふさわしい作家なんじゃないかと思うんです。また、佐伯さんのおっしゃった、絶えず自分の中で翻訳しながら小説の言葉を紡いでいくというのは、私も共感するところがあります。

松浦寿輝(まつうら・ひさき) 1954年、東京生まれ。詩人、小説家、東京大学名誉教授。2000年『花腐し』で芥川龍之介賞、2004年『半島』で読売文学賞、2017年『名誉と恍惚』で谷崎潤一郎賞、Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞。近著に『人外』。
松浦 先日、「令和」という新元号が発表されました。出典は国書である「万葉集」だと政府は発表していますが、そもそも「令」も「和」も漢字自体が中国からの渡来物であり、それを自分たちのものにして日本語を体系立ててきたわけですよね。そういう点において、日本語自体がクレオール的な混交言語だと思うんです。日本語で文章を書くということも、仮名と漢字の間で戯れながら、一種の複数言語的状況に身を起きつつ、言葉を綴っているような気がしています。
トランプ政権下で、翻訳文学が賞を受賞したことを嬉しく思う
多和田 私は今「星に仄めかされて」という作品を『群像』に連載しています。これは昨年4月に刊行された『地球にちりばめられて』の続編です。この作品は、留学中に故郷の島国が消滅してしまった女性を主人公にし、すでに日本もなくなってしまったんじゃないかというポスト危機を描いている。大きな危機はすでに過ぎ去っているんですね。

『地球にちりばめられて』多和田葉子
留学中に故郷の島国が消滅してしまった女性Hirukoは、ヨーロッパ大陸で生き抜くため、独自の言語“パンスカ”をつくり出した。Hirukoはテレビ番組に出演したことがきっかけで、言語学を研究する青年クヌートと出会う。彼女はクヌートと共に、この世界のどこかにいるはずの、自分と同じ母語を話す者を捜す旅に出る―。言語を手がかりに人と出会い、言葉のきらめきを発見していく越境譚。
一方『献灯使』は、静かな生活を送っているんだけれども危機であるという雰囲気が全体に漂っている。その作品が全米図書賞を受賞したというのは、もちろんアメリカ人のみなさんが読んでくださったからですが、同時に私は、アメリカは今、危機の時代なのだろうかとも考えたんです。もともとあまり翻訳文学を読まなかったアメリカという国が、トランプ政権下でますます外国から来る作品は読む必要はないと考え、それが国の政策にもなってしまっている。これはある意味危機的な状況です。

今回は新設された翻訳文学部門での第一回の受賞ですが、実は川端康成も全米文学賞を受賞しているんですね。この時は翻訳部門があったのですが、その後長らく中断されていた。それがこの時期になって翻訳文学部門として復活した。これは、アメリカ人なりの危機の時代への対応なのかな、と私は感じたんですね。翻訳された言語には何か違和感が残り、手触りがザラザラしているように読みにくさがある。今、アメリカの人たちが、面倒くさい、難しい、高いという翻訳文学を読もうとしている。そういう意味で、私はこの受賞を非常にうれしく思いました。
「危機」とは「更年期」と「思春期」を意味した
松浦 ところで古井さんは「危機」という言葉を、どのように感じられているかをぜひお伺いしたいのですが。
古井 危機というのはもともと“分かれ目”という意味らしいんですよ。クリティックという言葉はギリシャ語で「分かれる」という意味で、18世紀にはヨーロッパで「更年期」という意味を持っていた。だけど、「思春期」に対してもこの言葉を使っていたそうですよ。どの時期であっても、どっちに転ぶかわからない。危機ばかり意識していたら、生きてなんていられませんよ。毎日、一歩外に出たらどうなるかわからない。外的なことだけでなく、自分自身の心がどっちに傾くか、転げ落ちるかなんてわからない。そういう意味で、危機というものは日常に内在していて、危機があればこそ、人は生命力を保てているのではないか。危機の中からこそ力が出てくる。

古井由吉(ふるい・よしきち) 1937年、東京生まれ。71年「杳子」で芥川賞受賞。83年『槿』で谷崎潤一郎賞、87年「中山坂」で川端康成文学賞など。88年から19年間、芥川賞の選考委員を務めた。近著に『この道』。
古井 僕はめっきり足が不自由になって、行動範囲はみるみる狭まって、こもりっきりの暮らしになってしまった。パスポートだってとうの昔に切れた。だけど、こういう状況になってようやく感じられることがあるんです。
人は過去、現在、未来と生きますよね。僕もそうやって生きてきた。でも、果たして過去は本当に過ぎ去ったものなのか。むしろ過去のほうが現在なんじゃないか。それに引き換え、現在というものは過去や未来に侵入されて、とりとめのないところがある。過去、現在、未来が共存するような不思議を毎日噛み締めながら生きている。
あれこれしてきた、言ってきたことが本当なのか? 自分が知らずに言っていたことや、自分で思って忘れ去ってしまったことのほうが実は本質を突いているんじゃないか? それに自分の行動も、ずいぶん遠くまでほっつき歩いているようでいて、実はそんなに遠いところまで行ってないんじゃないか? 限界域のかなり手前で引き返しているんじゃないか? そう思う一方で、実は限界域を超えてしまったこともあるんじゃないか?
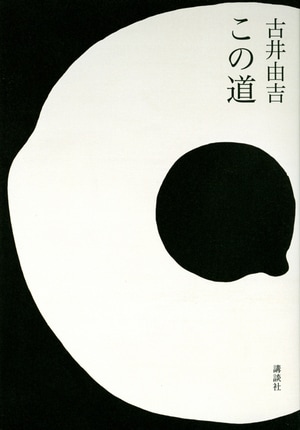
『この道』古井由吉
祖先、肉親、自らの死の翳を見つめながら、綴られる日々の思索と想念。死を生の内に、いにしえを現在に呼び戻す、幻視と想像力の結晶。80歳を過ぎてますます勁健な筆を奮い、文学の可能性を極限まで拡げつづける古井文学の極点。
- 1
- 2





















Comment