死がもたらす関係性からの解放
小川さんは言います。
「母が亡くなった時は、ずっと繋がれていた透明な“へその緒”みたいなものが消え、解放されたように感じましたが、同時に今度は母が自分の体内に入ってきて……それからはずっと一緒にいるような感覚です。死は悲しみや喪失感も伴いますが、人生を劇的に反転させるものにもなりうるんだなと」
ふと思ったのは、世の中に多かれ少なかれいる支配的な母親もまた、自分なりに考えた母親という「役割」を懸命に務めようとしていただけなのかもしれないーー母親にとっての「死」は、そこからの解放だったのかもしれません。「そうなんですよね」と答えた小川さんは続けます。
「すごく不思議なんですが、母が亡くなって何日間かした頃、トイレに置いていたちっちゃい鹿の木の置物が、どうしたってそこに落ちないよねという場所に、戻しても戻しても落ちているんです。夫に”ふざけてる?”と聞いたけれど”僕じゃない”と言うし。いろいろ考えて、もしかしたら母なのかな、こんなことできるようになったよ!って言いたいのかな、って。生前の彼女の私に対する行動も、彼女なりの、かまって!褒めて!というメッセージだったのかもしれない。だからそれ以降は、同じことが起きたびに、すごいね!すごいね!!って心の中で、母を褒めるようにしているんです」

ちなみに、お母様の最後のおやつは、何年かぶりに「買ってきて」と言われたケーキだったとか。
「普通なら皆がそろって準備して……となるところなのに、パッと見たらもう食べてて、うわあ、と思いました(笑)。ずっと何も食べれられなかったのに、よっぽど食べたかったんだなって」
本の中に描かれる様々な「最後のおやつ」。その病状ゆえに、リクエストした当人たちが食べられないことも。でも大事なのは、食べる・食べないではなく、誰かがそれを用意してくれたという行為そのものです。小川さんは自身の最後のおやつ「おばあちゃんのホットケーキ」を選んだ理由を、こんな風に語ります。
「祖母は明治の生まれで、ケーキと名のつくもの作ったのはその時がきっと初めて。私の中には、その味ではなく、作ってくれたそのことがすごく嬉しかったという記憶が残っています。”食べたい”のは、その味ではなく、その記憶なんだと思うんですーーむしろちょっと焦げてた、ちょっと失敗作だった、でも一生懸命作ってくれた、というような。”自分の人生は辛かった”と言う人だって、きっとよくよく探せば何かしら、“おやつの記憶”ってあると思いますよ」

小川糸 1973年生まれ。2008年『食堂かたつむり』でデビュー。以降数多くの作品が様々な国で出版されている。『食堂かたつむり』は、2010年に映画化され、2011年にイタリアのバンカレッラ賞、2013年にフランスのウジェニー・ブラジエ賞を受賞。2012年には『つるかめ助産院』が、2017年には『ツバキ文具店』がNHKでテレビドラマ化され、『ツバキ文具店』と『キラキラ共和国』は「本屋大賞」にノミネートされた。その他著書に『喋々喃々』『ファミリーツリー』『リボン』『ミ・ト・ン』など。
『ライオンのおやつ』を試し読み!
スライドしてお読みください。

『ライオンのおやつ』
小川 糸 著 ポプラ社
人生の最後に食べたいおやつは何ですか――
若くして余命を告げられた主人公の雫は、瀬戸内の島のホスピスで残りの日々を過ごすことを決め、穏やかな景色のなか、本当にしたかったことを考える。
ホスピスでは、毎週日曜日、入居者がリクエストできる「おやつの時間」があるのだが、雫はなかなか選べずにいた。
――食べて、生きて、この世から旅立つ。
すべての人にいつか訪れることをあたたかく描き出す、今が愛おしくなる物語。
取材・文/渥美志保
構成/川端里恵(編集部)

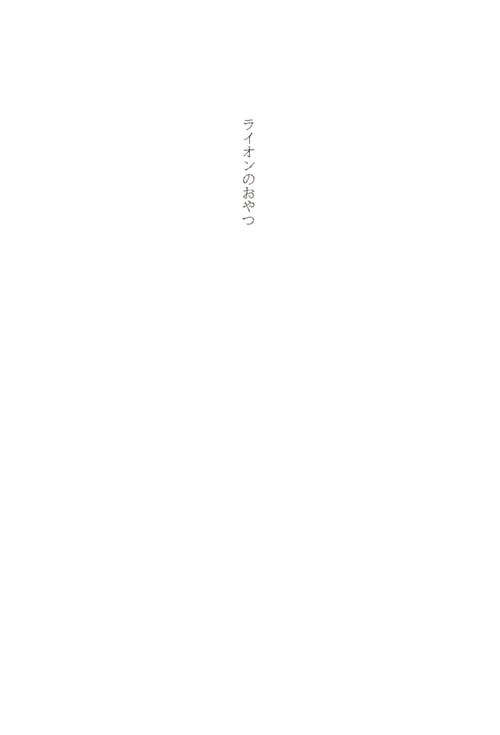






































Comment