貯金だけを趣味に生きてきた40歳独身女性の主人公が、検診で余命宣告を受ける。もう節約しなくていいならばと男をかってみたら――。作家・吉川トリコさんの最新刊『余命一年、男をかう』の刊行を記念して、4人の人気作家、エッセイストらが「もし余命一年だったら……」を綴るリレー連載がスタート。トップバッターは吉川トリコさん。著者本人ならどう過ごす?

低く流れる
43年間生きてきて、死にたいと強く思ったこともなければ、生きたいと思ったこともない。もちろん酒を飲んでやらかした次の日なんかに二日酔いに苛まれながらごくごくカジュアルに「死にたい……」と感じることはあるし、休日にサウナ×水風呂3セットを決めてから生ビールをくっと引っかけ、「この一杯のために生きているッッ!」と思ったりなんかもする。だけどそういうんじゃなくて、自分でもあずかり知らぬところからこんこんとわいてくる希死念慮や生存本能のようなものを感じたことは一度だってない。
ゾンビや殺人鬼や自然災害から逃げ惑うようなパニック映画や、戦争映画、クライムサスペンスなど、フィクションで描かれる過酷な状況を見るたびに、こんなしんどい思いをするぐらいだったらすぐさま死を選ぶと思ってしまう根性なし。それが私である。
生きる目標もなければ積極的に生きたいわけでもないが、毎日はまあまあ楽しいし、ひとまずのところは死ぬ必要を感じていない。いまの状態をありのまま表すとしたらそんなとこだろうか。貧困や病気や老後の不安はつねにべったり張りついているが、いざとなったら死ねばいいと考えるだけで、すっと気が楽になる。とはいえ、なるべく他人に迷惑をかけず、お手軽に死ねる方法が現状、日本にはあまりなさそうなのが問題なんだけど。
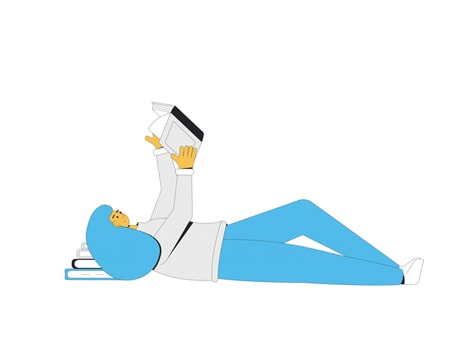
もし余命一年だったらどうするだろうかと考えてみたが、ひとくちに余命一年といってもいろいろある。病院のベッドに縛りつけられて起き上がるのもやっとの状態なのか、日常生活は送れるが、行動や食事を制限しなければならない状態なのか、それとも日本の"余命もの"にありがちな、つやつやぱんぱんした若く健康的なヒロインのように、あちこち自由に飛びまわり、彼氏といちゃいちゃして、好きなものを食ったり飲んだりしてもとくに支障がなさそうだったりする余命一年なのかで話はぜんぜん変わってくる。
『余命一年、男をかう』も日本の"余命もの"の例に漏れず、非常に都合のいい余命一年システムを採用しているので、ここでもそちらを採用することにするが、そうは言ってももはや若いとはいえない年齢の中途半端にキャリアを重ねた小説家、子どももいなければペットもおらず、とくにやり残したこともなければ、ついこのあいだ『大奥』の最終巻も読めたのでもういいかなという気持ちではいる。私が死んでも夫が不便しないように手はずを整えておくこと、老後のためにせこせこ貯めたお金の遺贈寄付先を見つけておくこと、進行中の本があれば最低でも校了はしておきたい。死んですぐ著作権をフリーにできるものならしたいけど、そんなことは可能なんだろうか。
日常生活においてはなにかを新しくはじめるというよりはむしろ、これまでしてきたことをやめていくんじゃないかと思う。これまで生きるためにやっていたことすべてを。
健康とダイエットのためにしていた毎日の運動はまずしなくなるだろう。糖質制限なんかはまあバカバカしくてやっていられなくなるだろうね。お酒も朝から飲んじゃうし、お菓子ばっかり食べて野菜なんかいっさい食べない。掃除も洗濯も炊事もしない。風呂なんか入らないし肌のケアだってもう知らない。韓国語の勉強も、友人たちと週一でやっているオンライン勉強会もソッコーで終了。昔の少女漫画をベッド脇に積みあげて日がな一日シャンパンを飲みながら読みふける。質の高い最新の海外ドラマなんか見向きもせず、『HiGH&LOW』をひたすら流しっぱなしにして、それに飽きたら『美味しんぼ』のアニメでも見る。価値観のアップデートなんかしたくない。感動なんかしたくない。流れる水のように、転がる石のように、低みに向かってゆく。不摂生で多少余命が縮んだところで、こんな暮らしを続けていたら早晩倦むだろうからちょうどいい。あと一年で死ぬとなったら、推しへの興味も執着もどこかへ溶けてなくなるんじゃないだろうか。推しって生きてくために存在するものだから。
「明日死ぬと思って生きなさい。永遠に生きると思って学びなさい」
ガンジーの有名な言葉だ。
いやわかるよ? わかるけど、ゆうてもそんな、聖人みたいに生きられる人間なんかおらんくない? と俗人の私はどうしても思ってしまう。
いつのころからか私は生きるために小説を書き、小説を書くために生きるようになった。生活の糧を得るための労働という意味でもあるし、良い小説を書くために自分を良いほうに向かわせたくて日々努力しているという意味でもある。良い小説を書くということは、小説家としての余命を延ばすことでもあるから、そのための勉強やアップデートは欠かせない。永遠に生きることになったら、永遠にたんたんと続けていくだろう。
それでも余命一年なら、書きかけの小説があったとしても完成させたいとは思わない気がする。わからない。担当編集者によるかもしれない。未完のまま死んでしまったら申し訳ないから、なんとしてでも書きあげなければと思わせてくれるようなマイメンの顔がいま何人か頭に浮かんでいる。すごい。死にゆく小説家に原稿を書かせるなんて、とんでもない敏腕編集者じゃないか。
やっぱりもうしばらくは死にたくないかもしれない。

『余命一年、男をかう』
吉川トリコ ¥1650(2021年7月16日発売) 講談社
幼いころからお金を貯めることが趣味だった片倉唯、40歳。ただで受けられるからと受けたがん検診で、かなり進行した子宮がんを宣告される。医師は早めに手術を勧めるも、唯はどこかほっとしていたーー「これでやっと死ねる」。
趣味とはいえ、節約に節約を重ねる生活をもうしなくてもいい。好きなことをやってやるんだ! と。病院の会計まちをしていた唯の目の前にピンク頭のどこからどうみてもホストである男が現れ、突然話しかけてきた。「あのさ、おねーさん、いきなりで悪いんだけど、お金持ってない?」。
この日から唯とこのピンク頭との奇妙な関係が始まるーー。
撮影/杉山和行(著者近影)
イラスト/shutterstock
構成/川端里恵(編集部)





















吉川トリコ(よしかわ・とりこ)
1977年生まれ。名古屋市在住。2004年「ねむりひめ」で「女による女のためのR-18文学賞」第3回大賞および読者賞を受賞。同年、同作が入った短編集『しゃぼん』にてデビュー。『グッモーエビアン!』『戦場のガールズライフ』はドラマ化もされた(『グッモーエビアン!』はのちに映画化)。その他の著書に、『少女病』『ミドリのミ』『名古屋16話』『光の庭』『マリー・アントワネットの日記Rose』『マリー・アントワネットの日記Bleu』『夢で逢えたら』など多数。