貯金だけを趣味に生きてきた40歳独身女性の主人公が、余命宣告を受け男をかってみたら――。作家・吉川トリコさんの最新刊『余命一年、男をかう』の刊行を記念して、4人の人気作家、エッセイストらが「もし余命一年だったら……」を綴るリレー連載。
第2回は、『夫のちんぽが入らない』や『いまだ、おしまいの地』で知られるエッセイスト・こだまさんです。顔も素性も明かしていない覆面作家ならではの余命の過ごし方とは……。

顔のない書き手の最期
「あと一年しか生きられないと言われたら何をする?」という質問は「無人島にひとつだけ持って行くなら何?」と同じくらい苦手だった。差し当たって現実味のない「もしも」を面白く広げる力がない。昨夜見た夢の話題くらいの「へえ」で終わる。会話の中でその手の話を振られたら地獄だなと思っていた。
病気持ちで、「早く死にたい」と口にするくせに「死」を想像できない。漠然としている。そんな簡単に死なない。最終的に何とかなるだろう。そう思っていた。ずっと他人事だった。
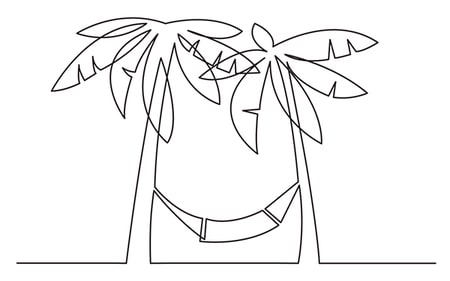
だけど、この春に一転した。父が癌の宣告を受けたのだ。
たまに「頭が痛い」と言って通院していたが、検査で異常は見つからなかった。歳を取ると誰でもガタが来るからね、と本人も家族も呑気に捉えていた。少し休めば回復するらしく、通学路の草刈りや雪かき、趣味の釣りにも出掛け、傍目には元気な七十代に見えた。
その間に首の骨や背骨がじわじわと蝕まれていたらしい。父は、いきなり難しい病名を告げられ、理解が追い付かぬまま入院した。コロナ禍で面会も叶わない。私は病名と生存率を検索して「こんなの見るんじゃなかった」と気が塞いだ。
「お父さん、本でも読めたら暇を潰せるんだけど、そういうのまるっきり駄目なんだよねえ。むかしから文字を読んでも内容を理解できない人なの。何を差し入れたらいいのやら」
困り果てる母を見て、ふと思った。
私の書いたエッセイなら読めるんじゃないか。
よくないことだと重々承知しているが、私は家族に内緒で家族の話を書き続けている。これまで本を四冊出したけれど、まだ家族はそのことを知らない。伝えていない。読んでほしいと思ったこともなかった。
だが、この局面で初めて心が動いた。
『父、はじめてのおつかい』(※『ここは、おしまいの地』収録)というエッセイを父に読んでもらいたい。
自分で言うのもなんだけど、生まれて初めて商業誌に掲載されたその短編を私は気に入っている。何の深みもない。ただ父の日常を淡々と綴った話だ。
六十を過ぎて初めてひとりで自分の服を買いに行ったこと、おつかいのメモが読めずに店員を呼んだこと、犬に噛まれて動物病院へ行き「ここはそういう場所ではない」と追い返されたこと。奇をてらわない父の行動がことごとく滑稽だった。
いくら読書に慣れていない父でもこれなら絶対に読める。どれもこれも身に覚えのある話だから。知ってる、これも知ってる。ぜんぶ俺の話じゃないか。そうなる。
父も私も心の内を素直に明かせない。お互い大事なことを言わずに生きてきたけれど、思うことはたくさんあった。本人すら忘れているような些細な出来事も記録してきた。
父の話を父に読んでもらいたい。意思の疎通が可能なうちに。
ぼんやりとしていた「余命」の輪郭に触れた瞬間だった。

前置きが長くなったけれど、それ以来、「死」が身近なものに変わった。
自分の身に置き換えて考えるようになった。
私が死んだら、こっそり書いてきた作品はどうなるのだろう。
まず、遺品整理に訪れた家族が次々とよからぬものを発見する。単行本、掲載誌、表彰状、明らかに本人と思しき人物が覆面姿でインタビューを受けている記事、読者からの手紙、私の似顔絵で作った大量のキーホルダー。それらは私の死以上のショックを与えるに違いない。あいつひとりでこそこそ何やってたんだ、と。
私は余命一年と宣告されたら、きっと「ありがたい」と思う。一年間も準備の期間をもらえるからだ。美味しいものを食べ歩くとか、旅に出るとか、そういった娯楽はこの際どうでもいい。自ら始めた匿名活動の後始末に取り掛かる。

自分のことしか考えずに書いてきた日々を心の中で詫びながら、この先も生き続ける人たちに何ができるか考える。創作にかかわるすべてのものを処分するか、信頼できる関係者に遺品として託すか、ひとりひとりに頭を下げて歩くか、それぞれに詫び状を残すか。
黙って作品に登場させてきたのは家族、親族、同級生、恩師、近所の人、職場の人たち。数え切れない。
たとえば、小学校から高校まで同級生だった男の子。私の容姿をからかい続けた彼との十数年の話を書いた。川本という仮名を使ったが、本当は山本という。私は創作と現実の開きが単語の置き換えくらいで、中身をたくさんいじるくらいなら書かない方がいいと思っている。誰にも活動を告げず、できるだけ本当のことを書いている。でも、そんなこだわりは決して褒められるものではない。
どこに住んでいるかわからない彼を探し出し、すべてを伝えて軽蔑されるべきか、このまま静かに消えるべきか。打ち明けて自分だけすっきりするような真似は許されない。
このようなものを書いて発表してしまいました。死ぬ前に伝えに来ました。死後、何かのきっかけで明るみになるかもしれず、心をざわつかせてしまうかもしれない。いまのうちに思い切りなじってくれないか。そんな謝罪行脚になるかもしれない。
自らの死が迫るとき、デビュー以来ずっと考えている問題にようやく答えを出せる。
一時期かなり危なかった父は自力で散歩に出られるまで回復した。早まって本を手渡さなくてよかったと胸を撫で下ろしている。
『夫のちんぽが入らない』作者と演出家が語る「孤独への処方箋」はこちら>>

『縁もゆかりもあったのだ』
こだま ¥1430(太田出版)
「俺はたった今刑務所から出てきたんだ」
私たちは「えっ」と発したまま固まった。刑務所と監獄博物館のある街特有の冗談だろうか。膝の上に載せた「かにめし」に手を付けられずにいた。(中略)別れ際、おじさんが「これやるよ、餞別だ」と言って渡してきたものを広げてみた。それは首元や袖口の伸びきったスウェットの上下だった。
第34回講談社エッセイ賞受賞のエッセイストこだま、待望の新作は自身初となる紀行エッセイ。
どの場所でも期待を裏切らない出来事が起こり、そして見事に巻き込まれていくこだま。笑いあり、涙あり、そしてドラマチックな展開に驚く内容も。
網走、夕張、京都などにとどまらず、病院や引っ越し、移動中のタクシーなど「自分と縁のあった場所」について全20篇を収録。

『余命一年、男をかう』
吉川トリコ ¥1650(2021年7月16日発売) 講談社
幼いころからお金を貯めることが趣味だった片倉唯、40歳。ただで受けられるからと受けたがん検診で、かなり進行した子宮がんを宣告される。医師は早めに手術を勧めるも、唯はどこかほっとしていたーー「これでやっと死ねる」。
趣味とはいえ、節約に節約を重ねる生活をもうしなくてもいい。好きなことをやってやるんだ! と。病院の会計まちをしていた唯の目の前にピンク頭のどこからどうみてもホストである男が現れ、突然話しかけてきた。「あのさ、おねーさん、いきなりで悪いんだけど、お金持ってない?」。
この日から唯とこのピンク頭との奇妙な関係が始まるーー。
イラスト/shutterstock
構成/川端里恵(編集部)





















こだま
17年に実話をもとにした私小説『夫のちんぽが入らない』でデビュー。翌年『ここは、おしまいの地』で第34回講談社エッセイ賞を受賞。今年4月に紀行エッセイ『縁もゆかりもあったのだ』を刊行。