人には言えないけど、やめられない趣味というのが、誰しも一つや二つはある。僕の場合、携帯電話を手に通話をしているフリをして雑踏を歩く、というのがそれだ。
あくまで「フリ」なので、携帯電話は誰にもかかっていない。ただ、送話口の向こうに文字通りのイマジナリーフレンドがいると思い込んで、とりとめのない話をする。当然、リアクションは返ってこない。それでも「フリ」なので、さも相手から何か反応が来たような調子で話を続ける。
場所は、なるべく人通りの多いところが理想的。これだけたくさんの人がいるのに、僕を知っている人は誰もいない。茫洋とした孤独の中、誰にもつながっていない電話に向かって延々話していると心が落ち着くのだ。こんな世迷いごとをかれこれ15年以上ひっそりと続けている。
この時点で、読んでいる人たちがすーっとドン引きしている音が聞こえてくるのだけど、どうか最後まで読んでほしい。
この趣味に目覚めたのは、確か20代前半の頃。その日、僕は気分が沈み込んでいた。まだライターになる前。おそらくADを辞めてフリーターとしてプラプラしていた時期だったと思う。恋も仕事も何もうまくいかず、先の見通しもまるでない。塞ぎ込む気持ちを無理矢理奮い立たせようと原宿まで買い物に来たものの、新作の洋服を見てもちっとも気分が弾まない。僕は神宮橋の交差点近くの広場にある植栽の縁石に腰を下ろし、ぼーっと行き交う人を眺めていた。
目の前をひっきりなしにいろんな人が通り過ぎていく。若いカップルもいれば、高校生くらいの集団もいる。若者の街には不似合いなスーツ姿の中年も意外と多い。楽しそうに談笑を交わす人もいれば、iPodをお守りみたいに胸ポケットに入れて音楽を聴いている人もいる。世界は確かに息づいていて、空はいやに高くて、なんだか僕だけがこの世界から切り離されているみたいだった。
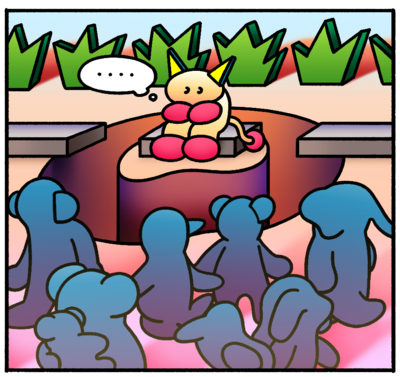
そのとき、誰かと話がしたい、と急激に思った。ガラケーを引っ張り出してみたものの、昼日中から無駄話に付き合ってくれそうな相手が思い浮かばない。連絡帳をスクロールする手をふっと止めて、僕は魔が刺したみたいにそのままケータイを耳に当てて、「もしもし」と口に出してみた。
当然、返事はない。当たり前だ。誰にもダイヤルすらしていないのだから。でもなぜか、誰宛てでもない「もしもし」が口からこぼれた瞬間、ケータイの小さなマイクの穴に吸い込まれ、どこか知らない世界へと運ばれていくような感覚がして、それが妙に気持ちよかった。
僕はそのまま「うん、久しぶり〜。いや、別に用ってわけではないんやけどな。何してるかな思って」と話しはじめる。「久しぶり〜」の相手が誰かなんて、僕にもわからない。特定の誰かを頭に浮かべているわけじゃない。ただ、なんとなく口からついた出まかせ。でたらめなエチュードを演じるようなつもりで、架空の友人とのやりとりを演じてみる。
「こっちは、まあぼちぼちかな。う〜ん、やっぱしんどいよ、東京。家賃も高いし」
「この間な、初めてあそこ行ってん。ほら、『グータン』でよく出てきた水槽のある店」
返球する相手のいないラリーは、不思議とぽんぽん言葉が出てくる。面白くなってきた僕は腰を上げ、原宿から青山方面へ進みながら無人の通話を続ける。
「そっちは? え〜、新しい人できたん。いや、ちょっと待って。その前に、前の人とはどうなったん? え? いつ別れたん?」
「は〜? そんなん怒ったったらええのに、なんで許すん? 意味わからん」
架空の通話相手は、どうやら最近新しく恋人ができたらしい。前の男はいかにも優柔不断で、女の優しさにつけ込んで調子に乗るようなクズ男だったので、彼女の代わりに僕がさんざん悪口を言い募った。当然、すべて架空の話である。僕のガラケーは無口に時を刻んでいるだけだ。
- 1
- 2





















Comment