2013年末に発行されると、その衝撃的なタイトルが多くの人の関心を引き、またたく間にベストセラーとなった『嫌われる勇気』。2016年には第二部として『幸せになる勇気』も登場。現在、2冊累計で200万部突破という驚異的な売上げを記録している。この本は、アドラー心理学に基づいて“哲人”と“青年”が幸福への道を徹底的に討論したもの。人生の中盤に差し掛かり、子育てや仕事の環境にも変化が生まれ、「このままじゃいけない」、「ライフプランを設計し直したい」と模索する人も多いmi-mollet世代にとって、ヒントとなる話があるかもしれない。そう思い、本の著者でアドラー心理学研究の第一人者である岸見一郎先生に、mi-mollet世代の勇気の持ち方について伺った。

アドラー心理学との出会いは
子育てがきっかけ
すべての悩みは対人関係にある、人は無意識に「変わらない」という決心をしている、承認欲求を否定せよ……。
やや刺激的とも思える論を展開し、「そんなことはない!」「いやでも……」と、現代人の葛藤を引き起こしたアドラー心理学。岸見一郎先生がそのアドラー心理学に出会ったのは、1989年。当時は心理学といえばフロイト、ユングがあまりにも有名だったが、なぜあまり注目されていなかったアドラーに興味を持たれたのだろうか?
「その頃ちょうど息子が生まれまして。妻が1年の育児休暇を経て仕事に復帰することになったのですが、すぐには保育園に預かってもらえなかったのです。それで時間の融通がきく私が育児をすることにしたのですが、これが想像以上に手強かったのです……。仕事は子どもが寝ている間にすればいいと安易に考えていたのですが、いざ子どもが寝ると、私も眠たくて仕事にならない。その後保育園に預かってもらえたのですが、連れて行くのが一苦労。ご飯をなかなか食べない、服を着替えない、自転車に乗らない……。その頃、私にアドラーが書いた本を読むことを勧めてくれた友人がいました。
最初は自分のためにアドラー心理学を学んだのですが、学ぶうちに、『子育てとは大変だが楽しいものだ』と受け止められるようになり、息子との関係も劇的に良くなりました。そんな私の変化を見たまわりのお母さん方からも相談されるようになり、答えているうちに、『この教えをいろんな人に広めたい』と思うようになったわけです」
こう聞くとアドラー心理学とは、学べば生きることがラクになる魔法の学問のように思うかもしれないが、そうではない。「アドラーの教えを知ったからといって、子育ての問題がなくなるわけではありません。でも、問題にぶつかっても深刻にならなくなります」と岸見先生は言う。
mi-mollet世代には、子育てや仕事が少し落ち着いたことで自分と向き合わざるを得なくなり、「あれ、私には何もない」といった戸惑いにぶつかっている人も多い。そんな読者たちは、どうすれば深刻にならずに、新たな人生を模索していけるのだろう?
「『何もない』と思ってしまうのは、子どもに依存している人生だったからでしょう。子どものことばかり考える人生というのは、自分のことで悩みませんから、ある意味ラクなのです。でも子どもはやがて自立しますし、そうすると小さいときのようにかわいくはなくなる(笑)。そうして一人になって、『今までと同じに生きていたのではダメだ』と気づくのです。私はよくスーパーに買い物に行くのですが、そこではよく、母親たちが我が事のように子どものことばかり話している光景を目にします。子どもと自分の人生は違うというのに、子どもが小さいときは本当にそのことに気がつかないのです」
それは仕事に没頭する人生も同じだという。
「私の友人は51歳で、『この働き方でいいのかな』と気づき、違う仕事を探し始めました。もちろん給料は減ってしまいますが、それよりも自分が幸福であることを優先したのです。その勇気を持てる人はなかなかいない。でも、このままではいけないと思いながら漫然と過ごしてしまうことのほうが、辛いですからね」
成功を追い求めると幸せから遠ざかる
たしかに、幸せになるために踏み出すことは決してラクなことではない。しかし踏み出す踏み出さない以前に、私たちは一体幸せというものが何なのか、そこも漠然としているのが実情ではないだろうか。そこで岸見先生に、アドラーの説く“幸福”についても伺ってみた。

「男性の人生を考えてもらったらヒントが見えてきますよ。男性にとっての幸せは単純で、“成功”です。だから多くの男性は定年退職するまでは幸せだと思い込んでいますし、『このままでいいのか?』などと悩んだりもしません。しかし定年後は、『何もない』と苦しむことになります。大事なのは人生の目標を“成功”に求めないことです。その点女性はもともと、人生の目標を成功には求めていない人が多いように見えます。地に足をつけて人生を考えているところがありますね」
では“成功”ともっとも遠いところにあるものといえば何か? それは子育てだと岸見先生は言う。
「無償の愛という言葉があるように、人は何の評価も報酬も求めることなく子育てという大変な行為をおこないます。何より子育て中は時間の歩みが止まり、社会とも隔絶して生きているように思います。でも満たされている。子育てに限らずそのような生き方こそが、幸福な人生と言えるのではないでしょうか。つまり幸福とは、何かを達成した先にあるものではなくて、今ここで手に入れられるもの。皆さんは、今すでに幸福なのです。ただそのことに気づけばいい。よく人生を充実させるために何か没頭できる趣味を持つと良い、といったことが言われますが、それはただ趣味に忙しくなるだけのことがあります。幸福は持てるものではない、流れるもの。人は何もしなくても幸せになれるのです」
私たちは今この瞬間から幸せになれる
では具体的に、どうしたら今すでに幸せであることに気づけるのか?
「過去を手放すのです。失われたものをどうにかして取り戻そうとするのが、過去に執着する最たる行為。たとえば人は年を重ねると、『美しかったあの頃に戻りたい』という思いを抱くことがあると思います。たしかに美しさは幸福に属するものですが、幸福と同様、流れるもの。衰えていくのではなく、ただ変わっていくだけです。そう思えない人が、年齢に不相応な美を追求します。真の美しさは年相応、質的なものなのです。若かった時の美に執着するのはやめましょう」
過去と同様、未来もまた手放すものだと岸見先生は言う。まだ始まっていない親の介護のことで悩むことも、家族が病気にならないか心配することも……。
「ある70代の女性のカウンセリングをしていた時の話ですが、今日のカウンセリングの要点をノートに書いてほしいと言われたのです。私はひと言、『人生を先延ばししたくない』と書きました。結局、人は今しか生きていないのですから、今できることをするしかないのです。たとえばガンになった夫の再発が心配だとしても、本当に再発するか、いつ再発するかは誰にも分からない。だったら今を一緒に過ごそう。そう思って、明日のことを思い煩わず生きるしかないのです」
過去と未来を手放す——、つまり今この瞬間以外のことを考えて不安にならないことこそ、幸せだと言えるのかもしれない。
「成功は“量”ですが、幸福は“質”です。質的なものは、誰も追随できませんし、奪われるものでもありません。だから幸福な人は、内面からにじみ出るような美しさを放っているのでしょう。そのように、“成功”を追求していたのでは幸福にはなれない、ということを教えてくれるのが子ども。そう考えると、子育てを経て『このままでいいのか?』と考え始めているmi-mollet読者さんは、真の幸福が何かを分かっていて、どこかで『あの子育てのときに流れるような人生を歩めたらいいな』と思っておられるのかもしれませんね」
mi-mollet世代ならではの幸せについて伺った今回。次回はさらに具体的に、mi-mollet読者が多く抱える人間関係(夫婦やママ友など)の悩みから、幸せになる勇気の持ち方について教えてもらった。目から鱗の話も出てくるので、是非ご一読ください!
後編は3月1日公開予定です。
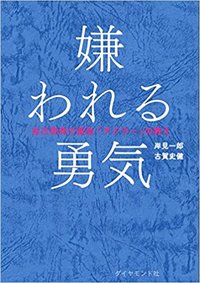
<新刊紹介>
『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』
岸見一郎、古賀史健 著 ¥1500(税別) ダイヤモンド社
フロイト、ユングと並び心理学の三大巨頭と称されるアドラーの思想を基に、“哲人”と“青年”の対話という形で、「どうすれば人は幸せになれるか」を提示した一冊。「トラウマを否定せよ」「すべての悩みは対人関係」「他者の課題を切り捨てる」「世界の中心はどこ
にあるか」「『いま、ここ』を真剣に生きる」の5章構成で、そのシンプルな真理は、読む前と後であなたの人生を変えるかもしれない……。

『幸せになる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教えⅡ』
岸見一郎、古賀史健 著 ¥1500(税別) ダイヤモンド社
『嫌われる勇気』の続編で、勇気二部作の完結編となる。「悪いあの人、かわいそうなわたし」「なぜ『賞罰』を否定するのか」「競争原理から協力原理へ」「与えよ、さらば与えられん」「愛する人生を選べ」の5章から成り、『嫌われる勇気』で提示された幸福への道を、具体的にどのように歩んでいけばいいのかを、同じく“哲人”と“青年”の対話形式で提示している。
取材・文/山本奈緒子 写真・構成/大森葉子(編集部)





















Comment