「ゆゆゆ、幽霊!」
からかってるのだろうか。しかし浅井さんはそうそう、というように頷いて、ご飯をぱくぱくと口に放り込む。
「そうなの。葬儀屋がねえ、幽霊見えちゃあおしまいよ。最初はね、時々火葬場なんかで妙な動きをしたり、何かを避けて歩いてるなあ、って思ってたんだけど。あるときね、小さなお子さんの葬儀で……涼森さん、気分が悪くなって倒れちゃってね。なんでも、その子の幽霊が、葬儀中お母さんの横にずっとくっついていて、いたたまれなくなっちゃったんだって。こう見えて情に厚いとこ、あるからね。それで辞めるっていったんだけど、社長がね、内勤ならいいだろうってうつしてくれたの。案外いいとこあるでしょ」
「浅井さん、辻さんが驚いてますから、そのくらいにしてくださいよ」
涼森さんは、表情を変えずにお味噌汁に蓋をした。
「えええ……あ、あの、幽霊って本当に? 見えるんですか? 話せるものですか?」
私は混乱して涼森さんに尋ねる。
「私は話せない。視えるだけ。何も役にも立たないのよ、それがもうびっくりするくらいにね」
涼森さんは、今日初めて、自嘲気味に笑った。
きっと、「視えるだけ」で、歯がゆい思いや怖い思いもしてきたのかもしれない。私はそれ以上きくのもはばかられて、「そうなんですね」と相槌を打ちながらもぐもぐとコロッケを口にはこんだ。
涼森さんは「最前線」から降りて、内勤に代われたことに満足しているようだった。幽霊がいるとも思わないけれど、もし本当に視えているならこの仕事はいかにも大変そうだ。だから現場ではなく内勤ができて、きっと彼女にとってはいいことなんだろう。この話はおしまい、というふうに口をつぐんだ彼女をみて、私はそんな風に感じていた。
悲しみと日常と
職場のひとはみないい人で、私は1か月も経たないうちに、だいぶ慣れることができた。実花も保育園に少しずつ慣れてきて、私たちは翔がいなくなってから初めて、生活のリズムというものが付き始めた。
もちろん寂しさは、ただ胸の底に沈殿しただけで、消えたりはしない。テレビを見たとき、音楽をきいたとき、いつも3人で歩いた道を歩くとき、その悲しみは泡立って涙になった。
浅井さんは相変わらず親切で、涼森さんは変わらす不愛想だったけれど、不思議とそのそっけなさが気にならなくなっていた。それよりも彼女の丁寧な仕事ぶりを感じて、私はただ、二人が同僚で本当に幸運だったと思いながら仕事をしていた。
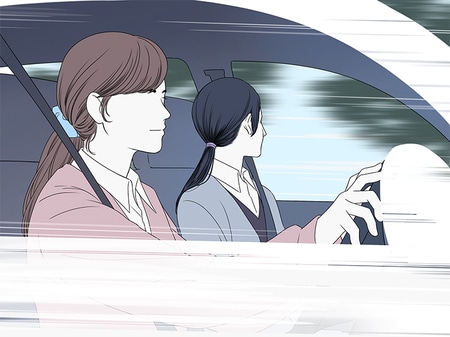
そんなある日、私と涼森さんは備品の買い出しを頼まれて、近所のイオンまで社用車を運転してでかけることになる。
後輩だから当然私がハンドルを握る。車が国道を発進し、助手席に座っている涼森さんはしばらく窓の外を見ていた。私はラジオをきくともなくききながら、慎重に運転をしていた。
「ねえ、辻さん。こんなことを言って気を悪くしないでほしいんだけど」
窓の外を見たまま、涼森さんが静かな声で話しはじめた。
「はい? あ、ごめんなさい、私また仕事で何かミスしましたか!?」
私は焦って、ハンドルを握りながら涼森さんのほうをちらっと見る。
「全然、そうじゃないの。……あのね、辻さんの家に、電話台、ってある?」






















Comment