夢が叶ったら、理想の作家像との違いに苦しくなった
そもそもご自身が「“こうあるべき”というのに縛られて、勝手に苦しくなってしまうタイプ」と語る宮西さん。小説の主人公と同じように作家を目指し、2016年に公募文学賞の受賞作で見事に作家デビューを果たした彼女ですが、その時も手放しで喜べなかったといいます。
「『夢がかなった! よかった!』となるかと思ったら、嬉しいだけではなかったのを覚えています。『めちゃくちゃ酷評されるんじゃないか』とも思ったし、『作家ならこれくらいのペースで本を出さなきゃダメでしょ』というのに縛られすぎて、自分がそうなれていないのが苦しかったり。主人公の美景の、掲げる理想が高すぎるところ、ちょっと極端なところは、自分と似ていますよね。例えば夫の雄大(ゆうだい)が鬱になったとき、<『会社を辞めていいよ』と言えるぐらい、自分がお金を稼げるようになりたい>と考えたり。もちろんそのくらい稼げたら理想だけど、二人で半々でやっていければいいじゃないですか」
かたや雄大を通じて描かれているのは、いわば「人生の方向転換」です。夢見ていた会社で働きながら鬱に陥った雄大は、「趣味が生きがいで、そのために働いている」という同僚を見て、人生を方向転換させていきます。
「ゴールを追い求めるだけの生き方をしていると、ひとつのゴールを超えた途端に次のゴールが必要になるし、その中で“どこまで行けばいいんだろう”と苦しくなったりもする。その生きづらさは、“そうじゃない生き方”をしなければ解消されないかなと思うんです。仕事の成功を諦めたっていいし、諦めたはずの夢をもう一度追ってもいい。“結婚をしない主義”だったけど“やっぱりしたい”でもいい。『そんなこと言ってなかったじゃん』って誰かに言われても、『心変わりしたから』『それは昨日の私だから』でいいと思うんです、それで生きやすくなるのなら」
二度と口をきかないと思った夫とのケンカも
日記に書くと笑い話になる

言葉にすることや物語を作ることは、物事を俯瞰して見たり、生きづらさの原因を深く考えるきっかけにもなると、宮西さん。作家ならではと思いきや、2年前から書き始めた日記にも、自身を見つめ直す機会をもらっているのだとか。
「コロナの感染者が増えていく中で、自分が言っていることが毎日違う気がして、その時の気持ちと一緒に書き留めておこうと。SNSでなくアナログなノートがいいのは、自分しか見ないから何を書いても、それこそ昨日言っていたことと違うことを書いても、誰にも文句言われないから。2年後の私が読み返すと、こんなことで悩んでたなんて馬鹿だなあと思うんですが、同時に“でも頑張ったね”とも思ったりして、これが成長しているってことなのかなとも思えるし。時には“いいこと言ってるじゃん”って思うこともありますよ。例えば作品にも使った、<『0か100か』で考えて、グレーゾーンじゃダメだって思ってませんか?>って言葉。2年後の私も“あ、また完璧にやらなきゃって思ってる”と気づかされました」
ちなみに「馬鹿だなあ」と思ったことは、「車の中にお菓子をこぼしたこと」を巡る夫とのケンカだったとか。
「私が一粒こぼしたら夫がすごく不機嫌になって。最初は『悪かったな』と思ったけど、だんだんと『食べたいって言い出したのはむこうなのに!』と腹が立ち、『もう二度と口をきいてやるものか!』って書いてる(笑)。2年後の私は『まあまあ落ち着いて』と思い、『こんなことがあった』と夫にも話しました。その場で言えばケンカになっただろうけど、振り返れば笑いのネタになってる。この小説も、そんな風に読んでもらえるといいかもしれません。生きづらい二人の不器用さを『かわいそう』でなく『なんでそうなるの?!』って面白がり、笑ってもらって、最終的に『よかったね』って思ってもらったら」
「ただ一緒にいるだけでいい」という気持ちが、恋愛の始まり
最終的に「よかったね」にたどり着けるのは、やっぱりこの小説が「純愛もの」だから。すれ違ってはいても、確かに夫婦は互いを思いあっているのがわかります。
「『ただ一緒にいるだけでいい』という気持ちが、恋愛の始まりという気がするんです。夫婦になり子供ができたりすると『好きなだけじゃ一緒にいられない』ってよく言うけれど、それでも『好きだから一緒にいたい』という気持ちを持ち続けるために、努力をしたいなって思うんですよね。それは『結婚しても化粧をする』とか『ファッションに気を遣う』とか、そういうことではなく、『相手が帰ってきたいと思える場所を作ること』なのかなと。日常を保つための努力というか」
なんで洗濯できないのかと攻めるより
パンツの枚数を増やせばいい
物語にはすごく印象的なエピソードがあります。美景は家事をてきぱきとこなすことができず、雄大の穿くパンツがなくなってしまいます。多くの人が「洗うこと」を求めるであろうその理由は、妻に(そして時には夫に)「洗う役割」を求めているから。でも雄大は「枚数が少ないのが悪い」とたくさんのパンツを買ってくるのです。
「以前『冷凍餃子は手抜きか?』という問題が議論になったとき、『愛情が感じられない』という意見がありましたが、役割にプラスして『俺(私)のことが好きなら冷凍じゃない餃子を作って』といった感情を推しはかるような感じかもしれません。でも相手が何で冷凍餃子を焼いたのか、なんでパンツが洗えないのか、そこを見てあげることも大切だと思うんです」

愛情の難しさは、互いが求める愛情の形に違いがあること。何が愛情なのかは、そこを踏まえた上でとらえなおす必要があるのかもしれません。
「例えばプロポーズでも、夢見ていた形ではないけれど、相手に愛があることは間違いないですよね。そのことを、受け取れるか受け取れないか。そこに愛があることを、認識できるかできないか。もちろんこうしてほしいということを言えれば、言ったほうがいいとは思いますが」
ちなみに「パンツを買ってくれるタイプ」の宮西さんの夫曰く「夫婦生活はあきらめが肝心」。それは決して捨て鉢なものではなく、そのままでいいよ、という優しい諦めです。極端なことを言えば、夫婦はいつだって止められるもの。それでもこの日常を続けていきたい理由はあります。
「例えば休みの日に何の予定もなかったら、朝起きる必要ってないじゃないですか。でも相手がいて、お腹減ってるだろうしご飯どうしようか、たまってる洗濯ものを洗わなきゃとか思うんですよね。自分のためには起きれないみたいな日もあるけど、相手がいるから起きられる。ちょっとプレッシャーだし、ちょっと面倒くさいんだけど、『ちょっと頑張ろうかな』って思えるのも相手がいるから。そんな気がします」。
【小説】新刊『毎日世界が生きづらい』の序章を無料試し読み!
▼横にスワイプしてください▼

『毎日世界が生きづらい』
宮西真冬 ¥1760(講談社)
メフィスト賞作家の新境地。
小説家と会社員。二人の幸せを探す物語。
「やっぱり、小説を書きたいよ。自分の本が書店に並んでいるところを見たい。私、器用じゃないから、全部をやるのは無理。……子供を産んで、作家になれなくて、『子供がいなかったら作家になれたのにな』なんて言うような大人にはなりたくないの」――本文より
あなたの居場所もきっと見つかる。
取材・文/渥美志保
構成/川端里恵
- 1
- 2

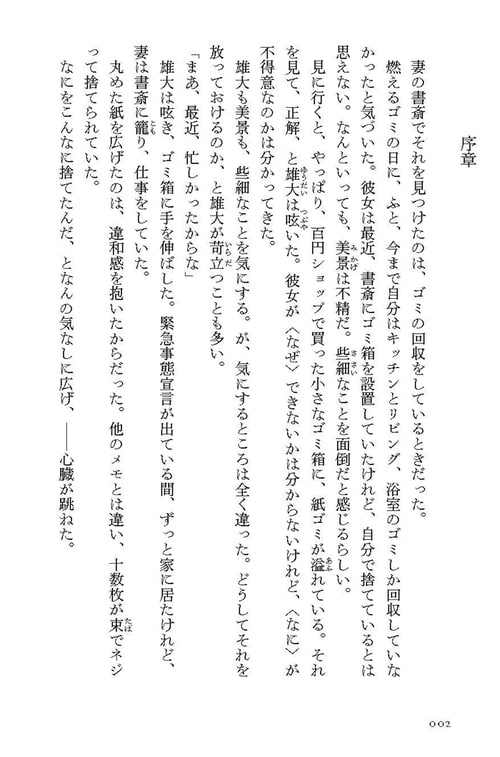


























宮西 真冬(ミヤニシ マフユ)
1984年山口県生まれ。2017年に第52回メフィスト賞受賞作『誰かが見ている』でデビュー。2018年『首の鎖』、2019年『友達未遂』で家族への複雑な思いと抑圧された人々のサスペンスを描く。今作は著者の新境地となる。