40代の男女なら、身に覚えがあるのではないでしょうか。
ふと過去の、青春時代の甘く苦い恋を思い出してしまったことが。
これはひょんなきっかけで思い出というパンドラの箱を開けることになった男・田中の、密かな告白。
「田中」はあなた自身かもしれないし、あなたの夫、あるいは過去の恋人たちの誰かかもしれない――。

名前:田中
年齢:40代後半
職業:そこそこ名の知れた男性作家
ずっと前から知っている女
「僕の前で、女が止まった。確かにそんな気がしたんですよ」
3月の第1金曜日。そこそこ名の知れた作家である田中は、連載小説の原稿を編集者に手渡すため新宿にいた。
待ち合わせまでの時間潰しで、彼はデパートにあるトイレ横の休憩スペースに座り、読みかけの文庫本を読んでいたという。
「勧められたアメリカ現代作家の本。でもこれがどうにも読みづらくてウトウトしていたわけです。そしたら視界の端にスカートから出た女の脚が映って」
一瞬、立ち止まった。しかしそんな風に思うのは、40代後半で独身・恋愛経験は過去に4度、それもここ数年途切れてしまった孤独な男の勘違いだと自分に言い聞かせた。
「だって、明らかに若い女性の脚でしたから。僕なんぞに用などあるわけない」
自嘲気味に言った後、しかし田中は困ったような、それでいて少々誇らしげな表情を浮かべた。
「でもね、トイレから出てきた彼女が再び止まったんです。僕の前で。さらに慌てた様子で目を逸らしたんですよ。確かです、これは。髪で隠れて顔ははっきり見えなかったんだけど……」
ずっと前から知っている気がした、と彼は付け加えた。そして、彼の直感は半分当たっていた。
謎めいた若い女の正体は……
「2ヶ月後、再び会った。同じ場所でね」
5月の第1金曜日。同じデパートのトイレ横休憩スペースで、件の若い女が待っていたという。
細かく説明すると、本当は田中のほうが先に休憩スペースにいたらしい。しかし「彼女とまた会えるかも」なんて意味のない期待をする自分がバカらしく、帰ろうと思いエレベーターに乗った。するとそこで彼女とすれ違った。
「いったんはそのまま乗って下に降りたんだけど……どうしても気になって戻った。そしたら彼女も僕のことを待っていたんだ」
そんな風に説明する田中の頬は紅潮している。
しかし一体、何の目的で?
20歳は離れた年上の男……「イケオジ」でもない、彼女から見れば枯れたおじさんであろう田中をなんのために待っていたというのか。
「もちろん僕も警戒しました。学生証を見せてくれ女子大生だってことはわかったけど、もしかすると裏組織に雇われた女かも……なんて突拍子もないことまで考えてね」
そういう彼の表情は、話している内容とは裏腹に生き生きしていた。
「しかしこっちはかなり年上の男なわけだし、動揺を悟られぬよう冷静に言ってやりました。御用件は、と」
すると彼女は、田中が想像していたよりももっと突拍子のないセリフを口にした。
「いやぁ、焦りましたよ。『私の顔、似ていませんか?』なんて言われたもんだから……誰に?私に?どういう意味だ?って怖かったな。冷や汗が出た」
田中は焦る心をひた隠し、ただ沈黙した。狼狽が顔に出ぬよう必死で、作家のくせにまるで言葉が出なかった、と彼は失笑しながら言った。
「そうしているうちに、彼女が痺れを切らしたように言ったんですよ。……真木山緑の娘ですけどって。息が止まるかと思いました」
真木山緑。
それは、もう忘れ去っていた過去……田中がまだ地元・下関の高校生だった頃の、初恋の女の名前だった。
▼横にスワイプしてください▼

『完全犯罪の恋』
田中慎弥 1600円(本体)
「私の顔、見覚えありませんか」
突然現れたのは、初めて恋仲になった女性の娘だった。
芥川賞を受賞し上京したものの、変わらず華やかさのない生活を送る四十男である「田中」。編集者と待ち合わせていた新宿で、女子大生とおぼしき若い女性から声を掛けられる。「教えてください。どうして母と別れたんですか」
下関の高校で、自分ほど読書をする人間はいないと思っていた。その自意識をあっさり打ち破った才女・真木山緑に、田中は恋をした。ドストエフスキー、川端康成、三島由紀夫……。本の話を重ねながら進んでいく関係に夢中になった田中だったが……。
芥川賞受賞後ますます飛躍する田中慎弥が、過去と現在、下関と東京を往還しながら描く、初の恋愛小説。
紹介文/安本由佳

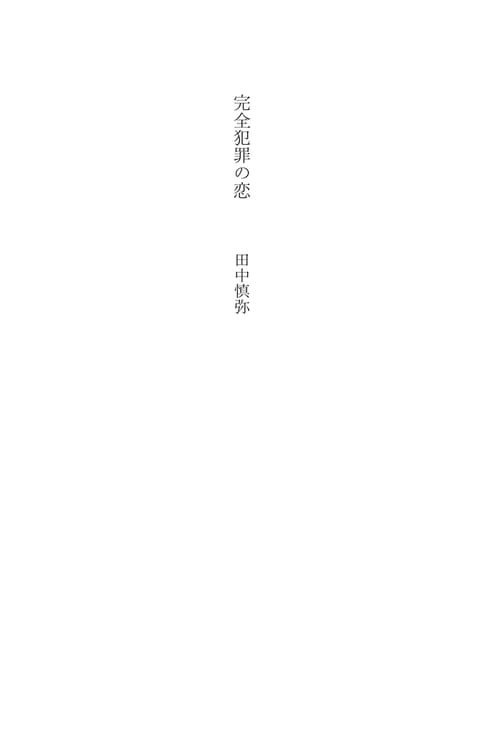





































Comment