きっとあの場に父がいたら、すかさず僕の頬を拳で殴っただろう。だけど運の悪いことにその場には母しかいなかった。
母は、あのとき、僕に向かって何と返したのだろう。「ごめんね」と小さく謝られた気もするし、ただ困ったように首を傾げていただけだった気もする。たぶん僕の方からデータ消去した。覚えていると、罪悪感で胸が破けてしまいそうだから、裂け目にテープを貼るように記憶に蓋をした。古びたVHSみたいに、記憶は何度再生してもそこで止まってしまう。最後に映った母はすっかり粒子が粗くなって、どんな顔をしているかまるで読み取れなかった。
ただ、母が怒らなかったことだけは覚えている。いっそ怒ってくれた方が楽だった。そしたら謝れるのに。「そんなこと思ってへんよ」と言い訳できるのに。母は決して怒りはしなかった。そんなところも、人より時間がゆったりとしている母らしくて苦しかった。
あれから30年経つけれど、僕はいまだにこのことについて母に謝っていない。母は、覚えているだろうか。忘れるはずはないと思う。もしも僕が親で、子どもにそんなことを言われたら一生忘れない。ずっと子どもに対する申し訳なさを抱え込んでしまっていると思う。母は、どうなのだろうか。聞くのが怖い。もしかしたら今聞いたところで、「そんなん忘れたわ」と言うかもしれない。それが、本音なのか、母の優しさなのか、知るのも怖い。
自分の傷は、自分で修復できる。大人になれば、自分のデリケートな部分なんていちばんよくわかっているから上手に回避できるし、いざとなったら麻酔の打ち方もわかる。
でも他人の傷はコントロールできない。自分がつけた傷は、今も跡が残っているのか。雨が降ると古傷が痛むように、時折思い出しては苦しめられているのか。わからないから、余計に怖くて、だから僕は今も人と深く付き合うのが苦手だ。

今でも母といると、隣に並んだわずか数センチの隙間に、30年前のこの思い出がひっそりと張り付いている。言えないままでいる「ごめん」の言葉が、いつも少しだけ僕の周りの空気を薄くさせている。いつか母に「ごめん」と謝れる日が来たら、何か変わるのだろうか。
こんなに大好きなはずなのに、思い出す母の笑顔は、笑っているようで、どこか寂しい。
構成/山崎 恵

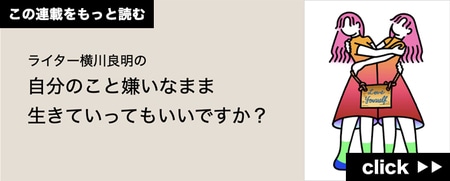































Comment