「俺が写した。だから……」
「おー達也。今日は自習室で残業か。頑張ってるな」
翌日。俺は授業がないにもかかわらず来ていた達也に声をかけた。時計は21時を指し、ほかの生徒は誰もいない。じつは今日は午後からチャンスを伺っていた。

「おー、先生。ちょっとさーこれ教えてよ。って算数は無理か~」
達也はノートを睨みながらしばらく考えていたが、今日は終わり~といいながら帰り支度を始めた。今しかない。
「なあ、達也。この前の合格判定模試のことだけど……。お前さ、アレ、社会めっちゃできてたけど」
我ながらなんて下手な聞き方なんだ。
「え? ああ、先週の模試か。なに、先生、どしたの急に。そんなに俺、できてた?」
「ああ。社会、95点。算数も123点。いつもできない社会が爆上がりしたから、校舎1位だ」
「マジ!? うっそ、やったー!!」
達也が嬉しそうに雄叫びを上げるから、俺はますます言いにくい。
「あれ? なに、どうしたの、褒めてくれないの?」
「……達也の答えと、亮介の答えなんだけどな、社会と算数がほとんど同じなんだ。俺が最初に気が付けばよかったんだけど、もう問題になってる。でも、俺が預かったから、本当のこと話してくれないか」
「……」
達也は、突然暗い目になり、うつむいて唇を噛んだ。
俺は、ひたすら達也が自分で口を開くのを待った。
「……ごめん。クラスが下がるのが嫌で。もうしないから……親には言わないで」
俺はしばらく、達也のまだ細い肩を見ていた。大人と子どものはざま、爆発的な成長期の直前。
その肩に、どれだけのプレッシャーを背負って勉強をしているのか、それはプロの俺たちが一番よくわかっていた。
中学受験は過熱しきっていて、子どもたちは3年も4年も努力を重ねる。親の期待を、校舎の期待を背負って、休むことは許されない。
「社会さ、達也が前の日までやってたとこ、テストにばっちりでたもんな」
「え……? なんで知ってるの?」
「ばーか、知ってるよ。必死で苦手なとこやっただろ? ずっと見てんだ、わかるんだよ、お前がどこを正解するかなんてさ」
達也の解答を、ファイルから取り出した。筆圧が強すぎて、消しゴムで必死で消して、また書いた、激闘のあと。
「……答えを写したのは、亮介だな? そうだとすると先生、亮介のお母さんに話をききにいかなきゃならない」
夏の夜、都会の怖いシーンを覗いてみましょう…。
▼右にスワイプしてください▼





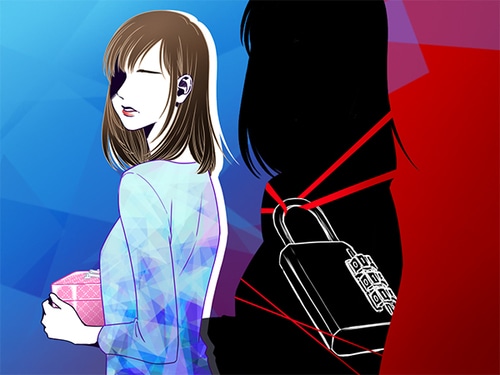



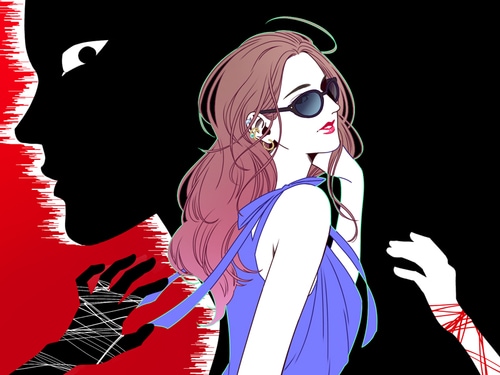
































![いま買って初秋まで使える「シャツ&ブラウス」おすすめの素材やデザインは?スタイリスト水野利香が解説![PR]](https://mi-mollet.ismcdn.jp/mwimgs/a/4/80/img_a4ab888660a4986eed6b44c379c032c0257273.jpg)









1