想像するに、普段から仲間内で僕のことをゲイだと噂していたのだろう。その流れで、彼はそうボケたのだと思う。悪意がないとは思わないけど、無邪気なボケなんだということはよくわかる。こういう程度の低いボケは男同士のコミュニケーションでよくあるし、たまたまその標的が僕だっただけ。そうわかってはいるけれど、ああやっぱりか、と指先に痺れのような痛みが走る。
彼は、カウンターに並んで座らされたのが気持ち悪かったと話していた。カウンターを選んだのは僕ではないんだけどな。むしろ不快に思われないように、なるべく椅子と椅子の間を離したつもりだったんだけどな。喉元まで出てきて、だけど絶対に口にすることはない反論を押し込んで、僕はトイレに戻った。それから二度と、彼とは話していない。
別に善人ぶるつもりでもなんでもなく、たぶん飲みに誘った彼の行為自体に揶揄の目的はなかったんだと思う。そして、一緒にいる時間を少なからず楽しんでくれたと信じたい。でもやっぱり人は集団になると、途端にコミュニケーションの形が変容する。それぞれに役割を設けたり、共通の敵や攻撃対象を探したり、コミュニケーションが円滑にまわるようにバランスを整える。僕はその調整役として、はじき出されたり、獲物にされやすいというだけのことなんだと思う。
きっとそれは僕の気質によるところもあって、そうならないためには自分をどうにか変えるしかない。昔は、回避策として一生懸命普通の人っぽく振る舞ってみたこともあった。でも、そうやったところで結局今度は自分が誰かをはじいたり、獲物扱いする立場に回るだけ。それがもうほとほと面倒くさくなって、僕は集団に関わるのはやめようと決めた。

フリーランスになって10年以上経つけど、不安定さと引き換えに得たメリットに、集団に混じらなくてすむというのは確実にある。この仕事は、直接やりとりするのは担当の編集さんのみ。1対1のコミュニケーションに集中していられるのは、とても心地の良いものだった。
ある夜、仲の良い編集さんと2人で酒を飲んだ。僕たちのテーブルの横には、4人組のサラリーマン。その中でいちばん若そうに見える、20代前半くらいの男性のサラリーマンが、その場ではいじられ役を買って出ていた。先輩の雑な振りもうまく拾って笑いに変えている。それを先輩は自分の手柄みたいに気持ち良さそうに笑っていた。先輩、今の笑いはあなたの振りがうまいんじゃなくて、後輩のカバーがうまいんですよ、と僕は心の中でツッコむ。
トイレに入ると、その後輩がいた。鏡を見るともなく見ている彼は、酒の場にいるときよりもひどくまったいらな顔をしていた。彼は楽しいだろうか。それとも苦しいのだろうか。鏡越しの表情からは読み取れなくて、横顔を盗み見ようとすると、彼はひと区切りづけるように息を吐いてトイレから出た。漂うオーデコロンの残り香が、道化を演じる彼には不似合いなくらい清潔だった。
構成/山崎 恵

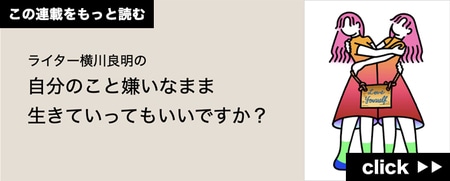































Comment